料理経験値0の僕が和菓子作りに挑戦するシリーズです。
今回は、『鬼灯』に挑戦してみようと思います。

お盆には必須ですね。
毎年、一番コスパ良く買えるお店を求めて、たくさんのお店をはしごするのが恒例行事となっています。
(というか、鬼灯(ほおずき)って、こういう漢字なんですね!)
で、作ってみたのですが、
個人的には、今までで一番出来の良い作品に仕上がりました!!!
それでは『鬼灯』を作っていきます。
1.練りきり【鬼灯】の作り方
①着色
緑色からオレンジ色に変わりかけの鬼灯を作ってみたいので、オレンジと緑色に着色していこうと思います。
使うのは、白あん2玉と、こしあん1玉です。

で、オレンジ色の食用色素を持ってなかったので、今回、新たに購入しました。
とっても良い色になったので、おすすめですよ!!
ついでに、いつも緑は抹茶を使ってたのですが、食用色素「緑」も購入しました。
抹茶での着色の仕上がり具合とは、あまり違いは感じませんでしたが、若干、食用色素の方が、白あん生地に馴染みやすい(=着色しやすい)気がします。
また、今回は、いつもと違った着色方法を試みてみます。
ネットで見つけたのですが、まず、少量の白あん生地に濃いめに着色した後で、残りの白あん生地を混ぜ合わせると綺麗に早く着色できる、とのこと。
なので、早速、少量の生地にまずはオレンジ色の色素を振りかけ、着色していきます。

コネコネしていきます。
こんな濃いめのオレンジになりました。

ここから、残りの白あん生地を追加してコネコネしていきます。

こんな感じになりました。

確かに綺麗な色になった!!!
でも、鬼灯の色には少し薄い気がしたので、もう少し色を足します。
もう少し赤色寄りになった方が良いかなぁ?とも感じたので、オレンジと赤を足します。

コネコネして、こんな感じになりました。

若干、濃くなったかな・・・・
これくらいにして、次は緑色を作ります。
まず、少量の生地に濃いめに着色します。

続いて、残りの白あん生地を追加します。

こんな感じになりました。

着色はこれにて終了です!!!
次は、包あんしていきます。
②包あん、形づくり
オレンジ色の生地と緑色の生地を、それぞれ円柱の形にして、隣り合わせます。

これを上からつぶしますが、オレンジの生地が緑色の生地の上に少し重なるように、角度を付けてつぶします。
こんな感じになりました。

オレンジ色の生地と緑色の生地の結合部分は、指を少し湿らせてから、オレンジ色の生地を引き伸ばしてぼかします。

ちょっとぼけたかな。。。
次に、これを裏返して、こしあんを包あんしていきます。

こんな感じになりました。

次に、こちらの球体を少し平らにしてから、側面が垂直になるように形を整えます。(もみあげ)
こんな感じになりました。

さて、ここからは茶巾を使おうと思います。
緑色が鬼灯の袋の先端の尖った部分、オレンジ色が茎につながった部分にしようと思います。
とりあえず、茶巾に載せます。

次にこんな感じで包みます。

ピントが合わなかった。。。
鬼灯の線が入るよう、茶巾のいくつかのシワが表面にくるようにしてます。
(↓この部分のこと)
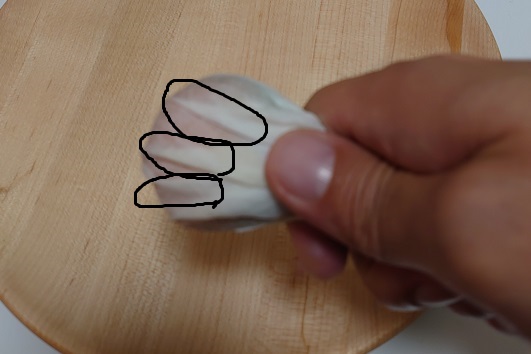
ここから、右手親指で強く押すと同時に、下記の矢印の方向に、左手人差し指の第2関節で少し押します。
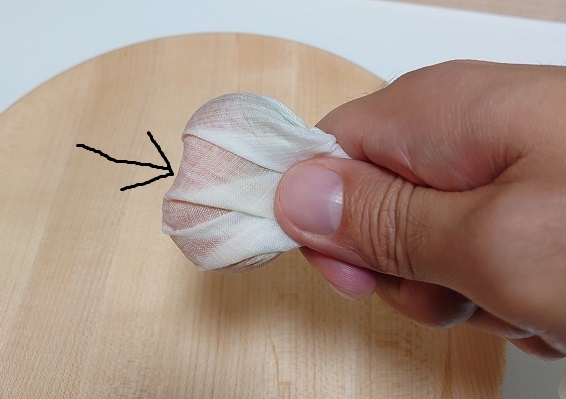
さて、茶巾から取り出してみます。
上手くシワができたでしょうか????

なかなか良い感じ!!!
(自己満)
緑色の先端部分を、鋭角に指で微修正します。
こんな感じになりました。

茎につながるオレンジ色部分のくぼみも、良い具合にできましたね(自己満)
ここまでなんだか良い感じにできたので、角度を変えて眺めてみます。


これで終わりでも良いのですが、茎を付けてみます。
(蛇足です。)

細い茎を付けました。
これにて完成です!!!
なんだか、色、形、ともに鬼灯らしく、かつ和菓子らしく出来上がった気がしています。
なので、お皿に載せて、また色んな角度から眺めてみます。
(余韻に浸らせてくださいなww)
(ダイソーの100円のお皿やけどな)




それでは、お抹茶とともにいただきます。
2.完成

中身はこんな感じ。

おいしくいただきました。
3.まとめ
今回は、『鬼灯』に挑戦してみました!!!
オレンジ色の食用色素良いですね。
色んな作品ができそう。
茶巾の絞り方次第で、色んな模様ができますね。
色んなパターンを研究していきたいなと思います。
工夫のしがいがありそう。
今回はここまでです。
それでは~~~
※しろあん、こしあんは「あんこの内藤」さんのものを使ってます!!
注文すると手書きのお手紙を頂けます☆☆☆
まとめ買いすればするほどディスカウントされるのでさらにお得!!



